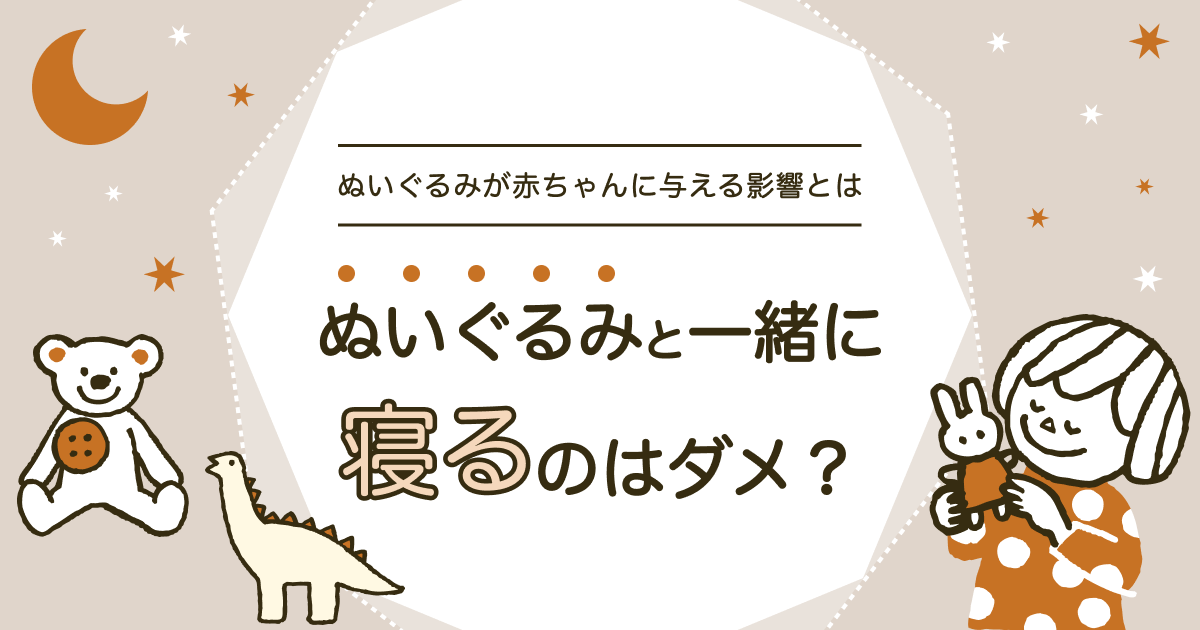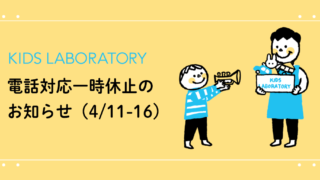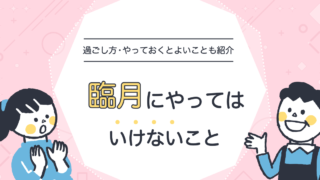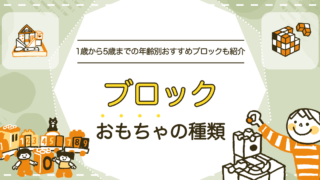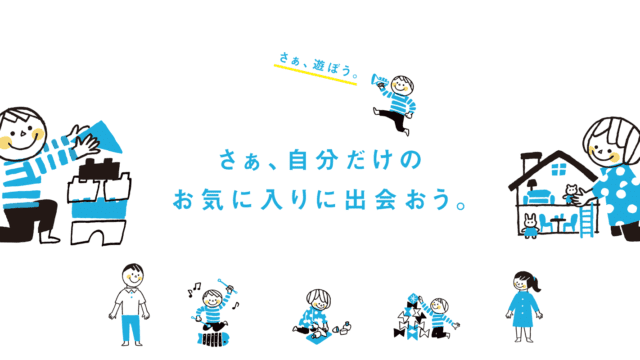目次
わが子がぬいぐるみを抱えながらすやすや眠っているのを見ると、微笑ましい気持ちになりますよね。
しかし、子どもがぬいぐるみと一緒に寝るのはよくない、ダメという意見も、世の中にはあります。
本当は、子どもがぬいぐるみと一緒に寝るのは悪いことなのでしょうか。結論をいうと、ダメではありませんが、小さな赤ちゃんにとっては危険なこともあります。
この記事では、子どもがぬいぐるみと一緒に寝ることのメリットや注意点についてまとめました。ぬいぐるみのじょうずな活用方法を学んで、子育てに活かしてくださいね。
ぬいぐるみが子どもに与える影響
子どもがぬいぐるみと接する姿は、かわいらしく微笑ましいものです。だからこそ、子どもへの影響を深く考えずにぬいぐるみを与えている方も多いはず。
ぬいぐるみは、ただかわいいだけの人形ではありません。子どもの成長にいろいろな影響を与えています。ここでは、以下の4つを中心に、ぬいぐるみが子どもに与える影響について見ていきます。
- 安心感が得られる
- 自立を促す
- 社会性や言語の習得
- 執着することもある
安心感が得られる
子どもがぬいぐるみを大事そうに抱えているのは、安心感があるからです。これはママやパから感じる安心感と同じようなもの。
赤ちゃんは、ママと一緒にいる時間がほとんどであり、そばにいることで愛着や安心を感じています。
ハイハイや歩くことを覚えて自力で動けるようになると、少しずつ親のそばから離れて活動するようになります。この姿を見て、親は子どもが自立したように感じるでしょう。
しかし、子どもにとって愛着や安心は欠かせないもの。親から得られなくなった安心感をぬいぐるみに求めるようになります。
特に寝るときは心細く不安な気持ちになりやすいので、ママが近くにいないときなどはぬいぐるみが手放せなくなるという赤ちゃんも多いんですよ。
自立を促す
ぬいぐるみは親からの自立を促します。
愛着や安心感を求める対象が、親からぬいぐるみに移行するのは自立心が育っている証拠です。
また、下の子が生まれたときや、幼稚園や小学校など新しい環境がはじまるときなど、自立を促されるタイミングでぬいぐるみを求めることがあります。
これは、強いストレスがかかっている状態から、情緒の安定を得ようとするためです。
ぬいぐるみを抱えた姿を見ると、赤ちゃんのような幼いイメージに捉えられがちですが、実は大きく成長している姿なんですね。
社会性や言語の習得
子どもにぬいぐるみを与えると、ぬいぐるみに名前を付けて会話をしている光景を見かけることもありますよね。これは、ぬいぐるみを通して相手の気持ちを考え、想像する学びになっているといえます。
子どもは大人の言動や自分にしてくれたことをよく覚えています。この体験をぬいぐるみを通して再現することで、言語の習得や親の愛情を理解し、社会性を学んで身に付けていくのです。
執着することもある
安心材料となるぬいぐるみを肌身離さず持ち歩く子もいるでしょう。
愛着は時に執着に変わります。大好きな母親を求めて、トイレにまでついてくるのと同じようなものですね。
ここで親が責めてしまうと、子どもはさらに不安になってしまうので、気持ちに寄り添って理解してあげることが大切です。不安が解消されていけば、次第に執着もしなくなりますよ。
ぬいぐるみは、子どものしつけにおいて重要な役割を果たしてくれます。
例えば、子どもがなかなか片付けをしないとき、直接子どもに伝えても素直に聞いてくれないことってありますよね。
そこで、ぬいぐるみに扮して子どもに問いかけたり、「一緒にやろっか?」と誘うことで、子どもは親に言われたときとは違った感覚になり、スムーズに受け入れることもあります。
また、子どもに伝えたいことを、あえてぬいぐるみに向けて親が話をすると、子どもは第三者の立場で聞けるので、納得してくれる場合もあるでしょう。
ぬいぐるみをうまく利用すれば、親自身も冷静に伝えられるので、落ち着いて向き合えますね。
子どもがぬいぐるみと一緒に寝るのがダメな理由は?
ベッドにたくさんのぬいぐるみを並べて寝るという子も多いでしょう。ぬいぐるみと一緒に寝るのは決して悪いことではありません。
子どもはぬいぐるみと一緒に寝ることで安心感を得られ、不安な気持ちやストレスを解消できます。
しかし、子どもの年齢によっては心配な部分もあるのが実際のところ。特に0歳~1歳の子には注意が必要です。
ベッドにぬいぐるみを置くことで発生する危険性は主に以下の3つ。
- 窒息の危険
- アレルギーや喘息の発症
- ベッドからの転落
それぞれ確認してみましょう。
窒息の危険
ベッド内にぬいぐるみを置いておくと、寝返りをうった際に鼻や口元を覆われてしまい呼吸ができなくなる危険性があります。寝返りができなくても、手足をバタバタとさせているうちにぬいぐるみが顔を覆っていたというケースも少なくありません。
これはぬいぐるみに限らず、ひも状の輪っかがついたものや、タオルケットなどにも同じことが言えます。
子どものお気に入りのおもちゃで悲しい事故が起こらないように、十分気をつけましょう。
アレルギーや喘息の発症
布団と同様、ぬいぐるみにもダニが発生します。ダニはフケ・垢・食べかす・ほこりを好み、ダニの死骸やフンはアレルギーの原因になります。
過度なアレルギー反応が出たり、喘息を起こしたりすると、お子様の命にかかわることも……。
このような事態を避けるために、ダニ対策やハウスダスト対策としてこまめな換気を行い、清潔な状態を心がけましょう。
ベッドからの転落
つかまり立ちができるようになると、ベッドの柵をつかんで立ちあがることもしばしば。
ベッド内にぬいぐるみがあると、それらを踏み台にして柵を乗り越え、ベッドから転落してしまう可能性があります。
ぬいぐるみに限らず、できるだけベッド内には物を置かないことを意識しましょう。
赤ちゃんや幼い頃であれば、ぬいぐるみを手放さず、いつも一緒にいるという姿も許容できますが、小学生や中学生、ましてや大人になってからも、「ぬいぐるみがないと寝れない」「ぬいぐるみを持ち歩いている」という人を見ると心配になりますよね。
幼児にとって、ぬいぐるみは移行対象の1つ。赤ちゃんの頃は母親がつきっきりの時間が多いですが、子どもが成長するにつれて、その時間は減っていきます。それにより、子どもは適度な欲求不満を感じ始め、不安や緊張を癒すための対象としてぬいぐるみを使用します。
これは、母親からの自立という点で子どもの成長には必要な現象だといえます。
ただし、それも長くは続かず5歳~6歳をピークに、移行対象への依存は減衰していくのが一般的です。
つまり、年を重ねてもぬいぐるみが手放せないというのは、ストレスフルな環境に身を置いていて、ぬいぐるみを逃げ場の対象と捉え続けているからだと考えられます。
ストレスや不安を緩和させる目的でぬいぐるみを利用するのは悪いことではありません。それよりも、ストレスとの付き合い方や環境改善に努めるほうが適切だといえますね。
(参考:富田昌平「乳幼児期の移行対象と指しやぶりに関する調査研究」)
ベッドにぬいぐるみを置かないほうがいい?
子どもの安全と健康を考えると、ベッドにぬいぐるみを置かないほうがいいのでは?と感じる方もいるでしょう。
しかしなかには、「ぬいぐるみと一緒のほうが子どもの寝つきがいいから置いておきたい……」と悩む方も多いはず。
確かに、眠るときに安心材料であるぬいぐるみが近くにあることで、子どもの寝つきはよくなります。
先述したようなデメリットは、親の一工夫で回避できます。ぬいぐるみの恩恵を受けつつ、危険要素をなくすことはできるので、ぬいぐるみと一緒に寝かせるのを辞めさせる必要はありません。
具体的に親がどんなことをすればよいかは次の章で解説しますね。
ぬいぐるみと一緒に寝かせるときの注意点
ぬいぐるみは子どもを寝かしつけるのに役立ちますが、ただ置いておくだけでは、想定していなかった事態が起きる可能性もあります。
そのような事態の発生を防ぐために、親ができることは主に以下の2つです。
- こまめな手入れで清潔に
- 子どもが寝たらぬいぐるみを移す
順番に詳しく説明しますね。
こまめな手入れで清潔に
ぬいぐるみを常に持ち歩いていると、どうしても汚れてきます。知らないうちに食べかすやよだれ、汗などが付着していることも多いですよね。
しかし、子どもから離して洗おうとすると嫌がることも。
そんなときは、「一緒にお風呂に入れてあげる?」と提案し、入浴時にお風呂場へ持たせてあげましょう。素材にもよりますが、お風呂で手洗いして脱水後、自然乾燥で十分きれいになります。
ダニ対策としては、布団乾燥機の使用や部屋の定期的な換気、湿気の除去が効果的です。
子どもが寝たらぬいぐるみを移す
子どもが寝るまでは、安心して眠れるよう、ぬいぐるみを近くに置いても構いません。子どもが寝たことを確認したら、そっとベッドから離しておくようにしましょう。
子どもが寝てしまえば、ぬいぐるみの役目は終わりです。ぬいぐるみがあることで、少なからず体まわりの自由が奪われます。しっかりと子どもが体を休められるよう、空間にゆとりを持たせてあげられるとよいでしょう。
ただし、夜中に起きてしまった場合、子どもはぬいぐるみを探したり、ぬいぐるみがないことでパニックになる可能性もあります。すぐにベッドへ戻せるところに置いておくのがおすすめですよ。
ぬいぐるみ選びのコツは?
子どもと一緒に寝かせるぬいぐるみは、安全なものを選ぶのが基本です。
赤ちゃんの寝かしつけに適したぬいぐるみの特徴やチェックポイントは以下の5つです。
- 縫製がしっかりされているもの
- 洗濯可能なもの
- 肌に優しい素材
- パーツが取れにくいもの
- 赤ちゃん自身が持てるサイズと重さのもの
ぜひ、購入時の参考にしてくださいね。
縫製がしっかりされているもの
赤ちゃんは力の加減をするのが苦手です。大人から見ると雑だと感じるような扱いをすることもあります。
簡単に糸がほつれてしまったり、中の綿が出てきてしまっては、長持ちしないのはもちろん、口に入れてしまうと誤飲にもつながります。丈夫なつくりのぬいぐるみを選びましょう。
洗濯可能なもの
赤ちゃんにぬいぐるみを与えるなら清潔に保つことが大前提。
手洗いは1つの選択肢ですが、パパさんママさんの負担を減らすことを考えると、手軽に洗濯機で洗えるものがおすすめです。洗う際は、洗濯ネットに入れてくださいね。
型崩れが心配な場合は、手洗いをおすすめします。
肌に優しい素材
肌触りがよいものは赤ちゃんも気に入りやすく安心できます。子どもはぬいぐるみを抱えたり頬ずりすることも多いので、やわらかい質感で安全な素材のものを選んでください。
万が一口に入れてしまうことを考え、素材や染料がオーガニックコットンのものがおすすめですよ。安全な上に繊細な赤ちゃんの肌にも安心です。
パーツが取れにくいもの
小さな飾りやボタンなどのパーツが付いていると、取れてしまった際に誤飲してしまう恐れがあります。
刺繍されているものであれば、子どもが触れ合う際に肌を傷つけることがないので安全です。
赤ちゃん自身が持てるサイズと重さのもの
ぬいぐるみでも、あまりに大きいものや重量があるものは避けましょう。
寝ている間に鼻や口周りが覆われて息がしづらくなることもあります。
片手で持てるサイズであれば、お出かけ時でも持ち運びやすく、子どもの気持ちも満たしてあげられますね。
子どもがぬいぐるみと接することで得られるメリットは多い
ぬいぐるみを子どもに与えるメリットは以下のようにたくさんあります。
- 自立への第一歩
- こどもの発達を促す
- 情緒の安定
- ストレスの回避
- 親がしつけを学べる
海外では、「ドゥドゥ」と呼ばれるお気に入りのぬいぐるみを、パートナーとして小さいころから大切に扱う習慣があります。
「ドゥドゥ」を大きくなっても自分の部屋に飾っておくことも珍しくないようです。
ぬいぐるみで遊んでばかりいるからといって、子どもから無理に切り離す必要はないのかもしれません。子どもが大切にするぬいぐるみを親も一緒になって大切に扱うことは、親子の信頼関係にもつながります。
安全に十分配慮をしながらも、子どもの暮らしにじょうずにぬいぐるみを取り入れていけるとよいでしょう。